こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。
以前のコラムでも解説した「相続登記の義務化」スタートより一年が経過しました。
制度の目的としては所有者不明土地を減らして行くことになりますが、一年経った現状はどのようになっているでしょうか。
そこで今回のコラムでは『相続登記義務化から1年経ってどうなった?』と題し、制度概要も含め、関連した各種制度についても今一度解説させていただきます。
不動産を相続することになりそうな方や、相続した方は参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記義務化の概要と背景
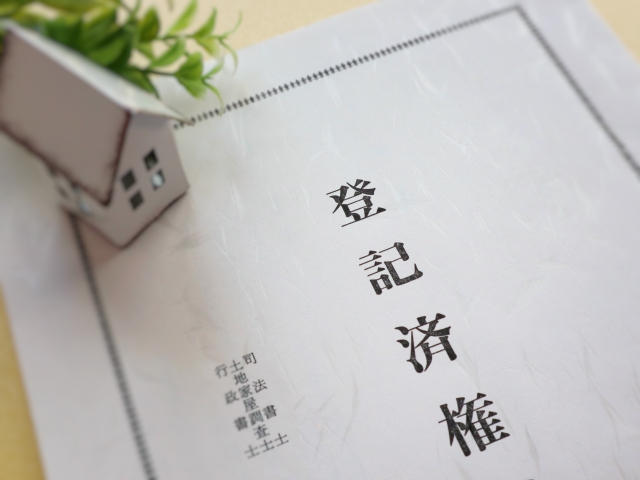
既述の通り、2024年4月より「相続登記の義務化」が本格的にスタートしました。これは、相続によって不動産を取得した場合、3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられるという制度です。登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。本制度は過去の相続にも遡って適用されますので、相続登記をまだ行っていない場合は令和9年3月末までに登記を行わないと過料の対象になる可能性があります。
冒頭でもお話した通り、この制度はいわゆる「所有者不明土地」問題の解決を目的としています。所有者不明土地が増加すると、国や自治体が再開発を進める際こうした土地が妨げになるケースもあり、災害時の避難や復旧の妨げとなるリスクも指摘されてきました。
こうした課題を受け政府は相続登記を義務化することにより、権利関係の明確化と適切な土地管理を促進する方針に転じたのです。
相続人申告登記
義務化に合わせて、「相続人申告登記」という新しい手続きも導入されました。これは、遺産分割協議がまとまっていない場合など、すぐに相続登記を完了させることが難しい場合に活用できる制度です。
この制度では、相続人が「自分が相続人である」と申し出ることによって、登記官がその情報を登記簿に記載します。ただし、この段階では所有権の移転登記ではないため、不動産を売却することはできません。あくまで、義務化された「3年以内の対応」を形式的に満たすための措置であることに留意が必要です。
申請には、法務局への申出と被相続人との関係を証明する戸籍謄本などの提出が求められます。登記の専門知識がなくても、比較的簡単に行える点が特徴であり、司法書士に依頼することも可能です。
「相続土地国庫帰属制度」で不要な土地を国へ引き渡す

一方で、相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば「相続土地国庫帰属制度」を活用して国に引き取ってもらうことも可能です。2023年4月から開始されたこの制度では、法務大臣の承認を得たうえで審査手数料(1筆あたり14,000円)と負担金を納付する必要があります。
負担金は、土地の種類によって異なります。たとえば、宅地や農地などは一律20万円、森林については面積に応じて計算されます。東京ドーム(約46,755㎡)と同じ面積の森林であれば、約59万円の負担金が必要となる計算です。 ただし、すべての土地が対象となるわけではありません。建物がある土地や、権利関係が不明確な土地、通路など第三者が使用している土地などは承認されない可能性が高いとされています。
制度の活用状況と課題
法務省によると、制度開始から1年で「相続土地国庫帰属制度」の申請件数は約3,400件、そのうち承認されたのは約1,400件にとどまっています。制度利用のハードルが高く、現状では十分に普及しているとは言えません。
また、制度を悪用する業者によるトラブルも報告されています。たとえば、「不要な土地を売却できる」と持ちかけ、高額な手数料や測量費を請求する悪質なケースも見られます。国民生活センターによると、相続登記義務化を契機にそうした相談が増加しているとのことです。
今回のまとめ

「不動産登記」とは「その土地や建物は自分のものです」と公にする手続きです。従って、ただ単に財産を受け取るというだけでなく、管理責任や将来的な負担も伴います。
相続する不動産が使われずに放置されれば、いずれは固定資産税などの負担が継続的に発生し、結果として“負動産”になってしまう可能性もあるのです。また、草刈り等の手入れを怠ったことによるトラブルリスクも大いに考えられることでしょう。
そのため、相続の発生が見込まれる場合は早めに親族間で話し合いを行い、誰が引き継ぐかを決めた上で、登記の準備をしておくことが重要です。必要に応じて司法書士や専門家に相談することも検討すべきでしょう。
所有者不明土地の問題や、負担だけが残る不動産相続を避けるためにも、今回の制度改正を機に「登記」と「土地管理」について一度しっかりと向き合ってみることが、将来のトラブル回避につながります。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。








