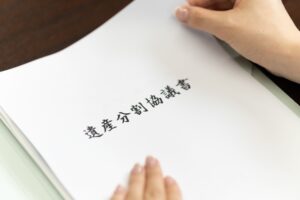こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。
当コラムでは2019年の相続法改正を機に新制度について解説を行ってまいりましたが、その中でも注目度が高い制度として「配偶者居住権」というものが存在します。
以前も少し解説したことがありましたが、今回は制度の概要から実際に利用する際のメリット・デメリット、さらに「利用した方が良いケース・避けた方が良いケース」までをわかりやすく解説します。
「遺された配偶者を守る制度」ではあるのですが、活用方法を誤ると大きなデメリットも存在しますので、利用を検討されている方はぜひ最後までお付き合いください。
配偶者居住権とは?

「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた自宅について、遺された配偶者がその家に住み続けられる権利を指します。
これまでは、遺産分割の際に自宅を売却したり、他の相続人へ持ち分を渡さなければならず、高齢の配偶者の生活が不安定になるケースが多くありました。
そこで新たに創設されたのがこの配偶者居住権です。これにより、配偶者は自宅に住み続けながら、遺産の公平な分割も実現しやすくなりました。
どのような場合に認められるのか?
配偶者居住権が成立するには、主に以下の条件があります。
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.被相続人が亡くなった時点で、配偶者がその建物に居住していたこと。
3.遺産分割や遺贈、または家庭裁判所の審判などにより配偶者居住権を取得すること。
つまり「亡くなった方の配偶者として同居していた自宅」についてのみ認められる制度です。
配偶者居住権のメリット

- 住み慣れた自宅に住み続けられる安心感
高齢の配偶者が環境を変えずに生活できることは、心身の安定に大きくつながります。 - 遺産分割の柔軟性が高まる
自宅の所有権を他の相続人に分けつつ、配偶者は「居住する権利」を確保できます。その結果、自宅の評価額を抑えられ、他の相続人との公平な分割がしやすくなります。 - 相続税の節税効果
配偶者居住権は所有権よりも評価額が低くなるため、相続税の課税額が抑えられるケースもあります。
注意すべきポイント

メリットの多い制度ではありますが、安易に利用すると後々トラブルにつながる可能性もあります。主なデメリットを以下にまとめます。
- 売却や貸し出しができない
配偶者居住権は「住む権利」に過ぎません。所有権がないため、その不動産を自由に売却したり、第三者に貸すことはできません。将来的に資金が必要になった際、柔軟に対応できない可能性があります。 - 不動産の利用価値が制限される
自宅の所有権を相続した子どもなどは、配偶者が亡くなるまでその家を自由に使うことができません。結果として「不動産の活用ができない」といった不満やトラブルが生じる場合があります。 - 権利は配偶者の生存期間のみ
配偶者が亡くなると居住権は消滅します。その後は所有者が自由に処分できますが、将来的に二次相続(例えば子どもが相続する際)で不動産の評価や処理が複雑になることがあります。 - 登記手続きが必須
配偶者居住権を第三者に対して主張するには登記が必要です。登記を怠ると、いざという時に「住む権利」を主張できない可能性があります。 - 遺産分割協議で揉める可能性
他の相続人からすると「自宅が使えない」「将来の売却に支障がある」といった不満が出やすい制度です。かえって争いの火種になることもあります。
具体例で考える
例えば、夫が亡くなり、自宅と預金が遺産として残されたケースを考えます。
- 自宅:3,000万円
- 預金:2,000万円
合計5,000万円の遺産です。
相続人は妻と子ども2人とします。妻が自宅を相続すると3,000万円分を取得したことになり、残り2,000万円を子ども2人で分ける形となります。この場合、妻は預金をほとんど受け取れない可能性が出てきます。
しかし、配偶者居住権を活用すると、自宅の「所有権」は子どもが取得し、妻は「居住権」を持つことで自宅に住み続けられます。居住権の評価額は所有権より低いため、妻は預金を多めに取得でき、生活費を確保しやすくなるのです。
ただし、この時に子どもから「自宅を自由に処分できないのは困る」と反発が出ることも少なくありません。このように制度の仕組みを理解せずに利用すると、相続人同士の関係悪化を招くことがあります。
配偶者居住権を利用した方が良いケース
- 配偶者が高齢で、自宅以外に住む場所や十分な資金がない場合。
- 子どもが既に独立して別居しており、自宅をすぐに使う予定がない場合。
- 相続財産の多くが自宅に偏っており、配偶者の生活保障を優先したい場合。
このようなケースでは、配偶者居住権を設定することで、安心して生活を続けられる可能性が高まります。
配偶者居住権を避けた方が良いケース
- 子どもが自宅に住む予定がある、または不動産をすぐに処分したい事情がある場合。
- 配偶者が比較的若く、将来的に住み替えや売却の可能性が高い場合。
- 相続人同士の関係が良くなく、制度利用がさらなる火種になると予想される場合。
このようなケースでは、配偶者居住権を利用するよりも、遺言書や生前贈与など他の方法を検討する方が適切です。
今回のまとめ

配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守るために新しく設けられた大切な制度です。しかし、メリットだけでなくデメリットも存在し、他の相続人の理解や手続き上の注意が必要です。安易に利用すると、かえって親族間のトラブルにつながる恐れもあります。
ご自身やご家族のケースに当てはまるかどうか、また実際に利用することが適切かどうかは個別の事情によって大きく変わります。制度利用については当事務所でもご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。