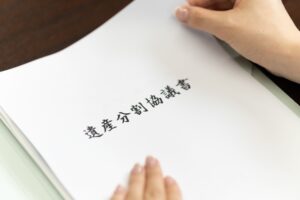こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。
「相続対策=毎年110万円までの贈与」という話は多くの方が耳にされたことのあるものだと思います。確かに、贈与税には「年間110万円まで非課税」となる基礎控除が設けられています。しかし、この制度を十分に理解せずに利用すると、思わぬ税負担やトラブルにつながる可能性があります。
そこで今回は「生前贈与と相続税 ~110万円の基礎控除だけではない落とし穴~」と題し、よく知られている基礎控除の仕組みと注意点、その他の贈与制度までをわかりやすく解説いたします。
これから相続対策として贈与を始めようと思う方は参考になると思いますのでぜひご覧ください。
暦年贈与と基礎控除110万円

贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。これを「暦年課税」と呼びます。
例えば、
・1年間に子どもへ100万円贈与した場合 → 課税対象は0円(非課税)
・1年間に子どもへ200万円贈与した場合 → 課税対象は90万円
この制度を活用して「毎年110万円ずつ子どもに贈与すれば相続税対策になる」と考える方が多いのです。
暦年贈与の落とし穴

年間110万円までの贈与は確かに非課税ですが、相続対策として考えた場合は注意しておきたいことが3つあります。詳しく見ていきましょう。
相続開始前の“加算期間”が7年に拡大(経過措置あり)
2024年1月1日以降の暦年贈与については、相続税の計算上、被相続人の死亡前7年以内の贈与が“持ち戻し”の対象になります。これは贈与ではなく相続財産として計算されることになるものですので注意が必要です。
2023年12月31日までの贈与は3年以内でしたので4年間拡大されたことになりますが、段階的な経過措置が亡くなった日ベースで存在します。
~2026年12月31日までに死亡:従来どおり3年以内のみ加算
2027年1月1日~2030年12月31日に死亡:2024年1月1日以降の贈与が加算(期間は死亡年によって3年超~最大7年弱)
2031年1月1日以降に死亡:死亡前7年以内の贈与を加算
さらに、延長された4年間(死亡前4~7年部分)の贈与については、総額100万円まで相続財産への加算対象外となる特例があります(100万円は“合計額から一度だけ控除”であり、年ごと控除ではありません)。 以上のように経過措置は存在するものの、「相続対策=年間贈与110万円」という単純な図式はこれまで以上に成立しづらくなっているのです。
形式だけの贈与は無効とされる可能性
「通帳・印鑑を親が管理し、子どもが自由に使えない」等は贈与不成立と判断されることがあります。贈与契約書の作成、受贈者名義口座への振込、受贈者による管理を徹底しましょう。
受け取る側の申告漏れに注意
基礎控除超の暦年贈与は受贈者(もらった側)が申告義務を負います。「非課税だと思っていた」という誤解が調査での指摘につながりやすい論点です。そのため110万円以上の贈与を受ける場合は前持って税理士へ相談すると良いでしょう。
ちなみに110万円はもらった側の年間総額です。財産を譲る側1人につき110万円ではありませんので注意しましょう。
相続時精算課税制度(2024年改正)

以前も当事務所コラムで解説したことがありますが、「相続時精算課税制度」という制度があります。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、2,500万円までの特別控除に加え、2024年からは毎年110万円の基礎控除が創設され、少額贈与の利便性が向上しました。
本制度は「2500万円まで贈与税は掛からないけれど、相続の時に贈与した金額を足して相続税を計算しますよ」というものです。制度改正により110万円の贈与税非課税枠を使いながら利用できるようになりましたが、一度選択すると原則として暦年課税には戻せず、将来の相続時に贈与財産を合算して精算する仕組みのため、利用は慎重に検討すべきと言えます。
教育資金や住宅取得資金の贈与特例
相続税対策の一環として活用される制度に、以下のような特例もあります。いずれも要件や期限もありますので、利用を検討される際はお気軽にご相談ください。
教育資金の一括贈与の非課税制度(最大1,500万円)
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度(最大1,000万円)
住宅取得等資金の贈与の非課税制度(最大1,000万円、住宅の性能により変動あり)
今回のまとめ

贈与のお話をすると、「いつから始めたらよいですか?」という質問は必ずお受けします。これは他の相続対策と同様、「元気でしっかりしているうちに」が基本です。
また、今回解説した通り贈与の制度そのものが“2024年以降は7年加算”と“経過措置”が加わり、設計の巧拙で結果が大きく変わります。形式的な贈与の否認、申告漏れ、そして家族間の合意形成不足にも注意が必要です。
ご家族の事情(資産構成・推定相続時期・受贈者の年齢やライフプラン等)に応じ、暦年課税・相続時精算課税・各種特例の組合せを最適化することが大切です。安易に「毎年110万円ずつ」で進めるのではなく、必ず専門家にご相談のうえ最新ルールを前提に計画的に進めてまいりましょう。
相続や贈与に関する具体的なご相談がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。