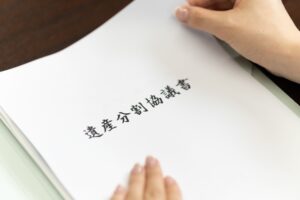こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。
先月のコラムでは相続の基本知識となる法定相続分と遺留分について解説させていただきました。今月のコラムではさらに基本に立ち返り、「相続とは何か?」という基礎から、「相続開始後の流れ」「放棄の選択肢」など、これから相続を考える方に向けたやさしい解説をお届けします。
相続とは?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、一定の範囲の人たち(相続人)が引き継ぐことです。
その財産には、現金や預貯金・不動産・有価証券などの「プラスの財産」はもちろんのこと、借金やローン・保証債務といった「マイナスの財産」も含まれます。
つまり、「相続=遺産をもらうこと」ではなく、「財産全体を引き継ぐこと」であり、借金を引き継ぐ可能性もあるという点に注意が必要です。
このため、相続が発生した場合には、「どのような財産があるのか」を正確に把握したうえで、「相続するかどうか」「どう分けるか」を判断することがとても大切になります。
相続の基本的な流れ

ここからは、相続が発生してから実際に手続きを終えるまでの全体像を時系列で詳しく解説いたします。特に相続放棄に関しては相続があったことを知った時から3か月以内と短く設定されているので、各手続きのスケジュール感を覚えておくことは非常に重要と言えます。
① 被相続人の死亡
相続は被相続人が亡くなった瞬間から自動的に開始されると言っても過言ではありません。
まずは死亡届の提出(7日以内)や、葬儀の準備など現実的な対応が必要です。ここでは、相続手続きの前段階として戸籍や住民票などの必要書類を整え始めると、後の手続きがスムーズになります。
② 相続人の確定(戸籍の収集)
次に必要なのは、「誰が相続人になるのか」を確定する作業です。
これは亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることで確認します。
特に再婚歴がある方や、前妻との間に子がいるケース、認知された非嫡出子がいるケースなどは戸籍を辿ることで初めて相続人が判明することもあります。
見落としや誤認があると後の協議が無効になる恐れもあるため、正確な調査が欠かせません。
③ 遺言書の有無確認
相続手続きの方向性を大きく左右するのが遺言書の存在です。
遺言書がある場合その内容が優先されるため、まずは自宅や金庫・公証役場に遺言書が保管されていないかを確認します。
自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認手続き」が必要になります。これをせずに勝手に開封すると、過料の対象となることもありますのでご注意ください。
④ 相続財産の調査
ここでようやく、相続する「財産の中身」を調査する段階になります。
調査対象は下記の通り非常に多岐にわたります。
・預貯金(銀行口座、証券口座など)
・不動産(自宅、賃貸物件、土地など)
・有価証券(株式、投資信託など)
・保険金(死亡保険、解約返戻金あり)
・借入金やローン
・保証債務
・未収金・未払金
・車両、貴金属、骨董品など
財産調査では、漏れがあるとトラブルのもとになりますし、逆に借金が多かったのに気付かず承継してしまった場合、大変な負担を抱えることになります。
我々税理士など専門家のサポートを受けることで、より正確かつ網羅的な財産の把握が可能になります。
⑤ 相続の承認・放棄の判断(3か月以内)
財産の内容が明らかになったら、相続するかどうかの判断をします。選択肢は主に3つです。
単純承認:すべての財産を引き継ぐ(何もしないと自動的にこれになる)
相続放棄:一切の財産を放棄し、相続人でなかったことになる
限定承認:プラスの財産の範囲内で負債を返済する
既述の通りこの判断は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、単純承認したものとみなされ、借金を含めたすべての財産を引き継ぐことになります。
つまり財産調査をいかに迅速に行うか? は非常に重要な要素となりますのでご注意ください。
⑥ 遺産分割協議と協議書の作成
相続を承認した相続人が複数いる場合、次は「財産を誰がどれだけ受け継ぐか」を決める話し合いです。これを「遺産分割協議」と呼びます。
協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し全員が署名・実印で押印します。この書類があることで、不動産の名義変更や預金の解約手続きが可能になります。
ただし、相続人の関係が複雑な場合や意見が分かれるようなケースでは、話し合いが長引くこともあります。早い段階での合意形成と、必要に応じた専門家の関与が円満な解決につながります。
⑦ 名義変更や財産の引継ぎ
遺産分割協議の内容に基づき、各相続人が受け継ぐ財産の名義変更を行います。
主な財産の引継ぎ方法は次の通りです。
不動産 ⇒ 法務局での登記変更
預貯金 ⇒ 銀行での解約・払戻し手続き
株式 ⇒ 証券会社での名義変更
これらの手続きには、協議書の他、戸籍謄本、印鑑証明書など複数の書類が必要になります。
⑧ 相続税の申告と納税(10か月以内)
相続財産の評価額が、「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合には、相続税の申告・納税義務が生じます。
申告期限は相続開始から10か月以内で、納税は原則として現金一括払いです。延納や物納も一定条件下で認められますが、事前準備が必要です。
今回のまとめ

相続は単なる「遺産分け」にとどまらず、法的・税務的な判断と対応が必要な非常に複雑で繊細な手続きです。
今回ご紹介した流れを頭に入れておくだけでも、「何を」「いつまでに」「どのように」行うべきかが明確になり、不安を減らすことができます。
相続についてお悩みのことがありましたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
一人ひとりの状況に寄り添い、最善の解決策をご提案させていただきます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。